その日は天気予報通りの酷い吹雪で、分かっていたのに俺達は、ツリーにするならヨーロッパアカマツじゃなくてやっぱりモミの木だろうと勢い込んででかけた。都会の地下を駆けめぐる下水の道の冷たさに慣れていたし、人よりちょっと厚めの皮を被っているから、ニューヨークの道路に水蒸気が立ちのぼり、道行く人のなびく髪を凍らせ、スタンドのホットドックを一瞬で冷凍にするような季節でも、いつも通り、この変わった体型を隠す程度の装いしかしていかなかった。
普段使いのバンの後部座席を取り除き、詰めてあった荷物を綺麗にどけた車内で、四人で目立たぬよう顔を伏せ、運転手役はサンタみたいな髭とかつらをつけてその手にはエイプリルから去年のクリスマスにもらった手袋をはめ、いつも通りの運転でアッパーニューヨークベイを横切るフェリーに車ごと乗り込んだ。広くなった車内でゆっくりと足を伸ばし、俺は紙の地図をひらいてこれから行って帰るだろう道を指で何度もなぞっていた。地図を見るのは好きだ。いま居る場所がそう大きくないことが分かれば、どんな問題もささいなことだと思えるから。
これから行く森にはモミの木の群生地があって、セントラルパークがまるごと入る大きさだ。横切る海の上、掲げた炎に雪を積もらせた憂い顔の女神が、どんよりとした雲の中に沈んで消える。
俺はじきに十六で、だから兄弟の中の誰よりも早く世の中を知らねばならない。そう思った。世の中というものが、俺の知る限りの情報で成り立っているならば、俺はこんな気持ちになりはしなかったし、本気で通せば嘘は本当になってしまうものなんだと知ることもなかったろうし、それで俺は、俺をとりまく全てのものに、ちょっとだけ期待しすぎていたことに気がつく。
今夜はクリスマス。地図上ではささいな問題である存在が、いまは俺の目の前で、があがあイビキをかいて寝ている。その足は助手席の肩にかけられ、助手席にいるミケランジェロがその片方に頭を預けて、これもまたよく眠っている。二人揃って朝までテレビでも見ていたんだろう。フェリーが港につくと、運転席にいたドナテロが、がるんとエンジンをかけて、港に渡された橋をゆっくりと下りはじめる。最後のところで敷居をふんだタイヤが持ち上がって、眠る彼の頭をバウンドさせた。あが、と開いていた口が言って、少し不機嫌そうに引き結ばれ、右へ左へ蠢いて体勢を変えると、またイビキをかきはじめた。港から側道へ出るとばたばたばたっと車のフロントガラスに雪が張り付いた。ドナテロがワイパーを作動させ、車内ヒーターの目盛りをぐるりと回した。ごおんと暖かい空気がヒーターの口から噴き出してきた。俺は揺れる車の中で明かりをつけてその下で地図をひろげ、窓から見える景色に目を走らせた。道の脇にある標識はどれも大量の雪が被さり、信号機にはつららが下がっていた。
「どこまできた」
「うーん、もう五キロくらい来たんじゃないかな」
俺は地図をたたんだ。助手席と運転席の間から身を乗り出し、カーステレオを入れた。どこの局も雑音だらけで、一番綺麗に音が入るローカルチャンネルはけだるいクリスマスソングを流していた。曲が終わると〝ただいま試験放送中です〟と平坦な声が言って、またスローテンポのクリスマスソングに戻る。
「たぶん合ってるとは思うけど」
「去年はコーラかなにかの看板があったと思う」
「んー、いまのところ見えないね」
「こんなに行かなかったぞ」
「そうだっけ」
まだ午前中だと言うのに空は一面灰色で、道は真っ新な雪の塀に挟まれてすごくせまく感じた。ドナテロは「まあ大丈夫でしょ」とのんきに口笛をふいている。そのうちにぽつぽつとあった民家もなくなり、両側は生い茂る杉の森になった。ドナテロが突然「あったあった」と方向指示器を左に倒す。俺は曇る窓をこすって外を見ようとしたが雪で大部分が覆われていて見えず、仕方なくドアについていたハンドルを回して窓を開いた。窓に張り付いた雪は氷になってそのままの形で残っていた。びゅうおお、と強い風が車内に入り込んできた。半分出した顔が風に殴られて感覚がなくなってくる。車は森へ続く小道に進路を変えた。そこには確かに大きな看板が出ていて、〝メリークリスマス〟の文字を電飾でチカチカ光らせていたが、それが前に見たものかどうか確認する前に車は道を曲がりきってしまった。ラジオから聞こえていたクリスマスソングも途絶えがちになる。ほの暗い森の中をライトを光らせた一台のバンが走っていく。俺は窓についた氷を取り払いながら、
「なあ、ほんとうに合ってるか」
「あってるよ。看板があったでしょ」
「ちゃんと見たのか」
「見たよ」
「でも」
ざあっとタイヤが擦れる音がして、背の高い森が途絶える。突然あたりがひらけたかと思うと、低いモミの木の群れが現れた。規則正しく植えられている幼木は、どれも黄緑色のふっくらとした葉をつけていて枝は隙間なく生えそろっており、デパートに並ぶ売り物のツリーみたいだった。ドナテロはいそいそと路肩に車を寄せて停車した。俺は開けていた窓を閉めて、冷たくなった頬を擦りながら、
「これは誰かが売るように育てたやつだ。勝手に持っていけないよ」
「なにいってんの。表示は?ほら、ないじゃない。僕がみつけたんだ、これはもう僕のだよ」
そう言ってドナテロは顔につけていたできあいの髭を取りさり、それを帽子の中に詰めて座席に置くと、隣で涎を垂らしていたミケランジェロの頭を叩いて起こした。ミケランジェロは、げくん、と妙な声をあげて目を開き、欠伸をしながらあたりの景色を見回した。そして、窓に手をついて少々うんざりしたように「さむー」と体を縮めて言った。ドナテロがさっそく運転席から降りてさくさくと雪の中を歩き始めたので、俺は仕方なく未だイビキをかいて寝ているラファエロの脛のあたりに手を置いてぽんぽんと叩いた。起きないので、ゆさゆさと揺さぶって「起きろ」と声をかけた。ラファエロは口をぱくんと閉じてまばたきし、両腕を伸ばして背伸びした。足に乗っていた俺の手がぐいと持ち上がる。そのまま彼は起き上がりこぼしみたいに上半身をはねあげ、ぐるりと向きをかえて、俺と向かい合った。俺の手はまだ彼の膝のあたりに乗ったままだ。彼は長袖の黒いシャツにグレーのスウェットの下という出で立ちで、その足には靴を履いていなかった。
「おまえ靴は」
「あ?」
「靴はどうしたんだ」
「ああ忘れた」
「どうするんだ外は吹雪だぞ」
「ちょっとだろ、平気だ」
ばたんと音がして、ミケランジェロが助手席を降りていく。ミケランジェロはトレーナーのうえにフードつきのジャケットを着て、足には長靴を履いている。俺は呆れてその膝を少し強めに叩いた。「なんだよ」とラファエロが唸る。
「何でもいいからはけ」
「なんだおまえ、真面目か。」
はっ、とラファエロは鼻で笑って、くるぶしまであったスウェットの下をふくらはぎまでまくり上げて、ドアを開けた。びゅおおおと益々強くなった風が雨と雪をまき散らせて車内に吹き込んでくる。ラファエロは後ろに積んであった工具の袋をとって、降り積もる雪の地面に足を降ろし、荷物を肩にかけて飄々と歩みを進める。俺はふうとため息をひとつ。見下ろせば自分もネルシャツ一枚にジーンズ、履いているのはメッシュ生地のスニーカー。彼とそう変わらない軽装だった。
俺はため息と共に車を降りた。吹く風に体を縮こまらせながら、前をゆくラファエロのあとに続いた。雪の中で、車のテイルランプがちかちかと点滅していた。ラファエロは目標が定まったのか、どんどん足が速くなってそのマスクのひらめき以外、あたりに立つモミの木とそう変わらない姿になってしまう。俺も慣れない靴で新雪に足をとられながら歩いていくがどうにも胸騒ぎがして、振り返って灰色の壁の向こうに車のランプがあるのを確かめる。ほっとして前に向き直るとラファエロの姿が見えない。冷たい空気が肺に満ちる。
そこへごうんと風が吹いた。モミの木の枝がしなって雪の塊に全身を殴られた。わ、と思わず声が出て、裂けるような痛みに襲われ俺は足をとめる。濡れたところから薄い氷が張りはじめ、てのひらで顔や腕を撫で擦って払い落とした。ざざっと足音がして閉じていた目を開けると、いつのまにか、少しだけ息のあがったラファエロが前に立っていた。ラファエロは俺と目が合うと急にかっと目尻をつり上げて、きびすを返し、大股で歩き出す。
あとを追って踏みだそうとした俺の足からずぼ、と、靴が脱げる。脱げた靴はあっという間に白い雪に覆われる。俺は靴と宙に浮いた片足と、遠ざかる甲羅とを天秤にかけて、結局靴はそのまま、冷たい雪を思い切り踏んで走っていって、彼に追いついた。ラファエロはゆうに4メートルはあろうモミの木の前で、肩をいからせて工具の入ったバッグの中身を開けているところだった。
「ドニーは、」
「さあな」
「探さないと」
「いいんだよ」
「俺たちを待ってるかもしれないだろ」
がらんがらんとわざとらしい音を立て、ラファエロはのこぎりやカナヅチの中から小ぶりの斧を取り出すと長い木の柄の部分を両手で持って重さを確かめるように二、三度持ち替え、俺をちらと見て、でも何も言わずに斧を振り上げがこん! と幹に打ちつけた。
「おい」
がこーん!
「話を」
がこーん!
「聞いてるのか」
がこーん! がこーん!
「ラファエロ!」
「っうるせえな! てめえで勝手に行けばいいだろガキじゃねえんだぞ! さっきからぐちぐちぐちぐちママ気取りか!」
頭がぱっと発光し、口を開けど言葉は出ず、吹雪は益々強くなってきて、足の感覚は鈍く、なのにラファエロはひたすら斧を打ち下ろしていて、俺はもう衝動のままにその腕を掴んで無理矢理彼の手から斧を引きはがした。「なにしやがる!」とどら声でわめいたラファエロが斧を取り返そうと柄を掴み、俺は離さず、彼も離さず、二人して雪のうえをどたどた踏み荒らしながらどすんっとどちらかの甲羅が木の幹にあたり、その刹那、ばりばりばり! と幹の裂ける音がして、みあげると大量の雪をのせたモミの木が、ゆっくりと倒れてくるところだった。
◆
気がつくと、俺は古い、木造の、みたことのない小屋の中にいた。下は土の地面がむきだしで、ところどころ霜が降りて白いものが混じっている。俺は何か堅いものの上に横たわっており、木の壁の向こうでごうごうとすさまじい風が吹き荒れているのが聞こえる。どこからか吹き込んできた雪が、俺の投げ出された手をうっすらと白く染めている。視線を巡らせるとすぐそばに緑のモミの木が、真っ二つに折れた状態で転がっていて、その向こうにラファエロが立っているのが見えた。鉄でてきた古い暖炉を前にして、のこぎりと、切り出したばかりの木の枝を持ったまま「……なんでつかねえんだ……」とぶつぶつ独り言を言っている。体を起こそうとすると、頭に激痛が走った。呻き声にラファエロが気がついて俺をみる。眉間に深い皺を寄せ、ばつが悪そうな顔で彼は言った。
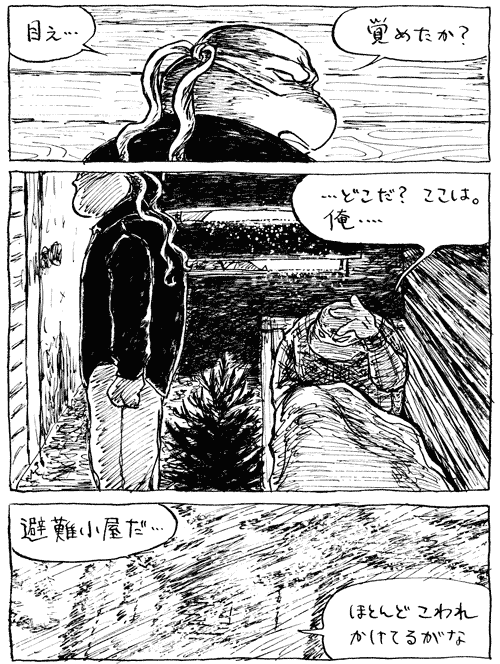


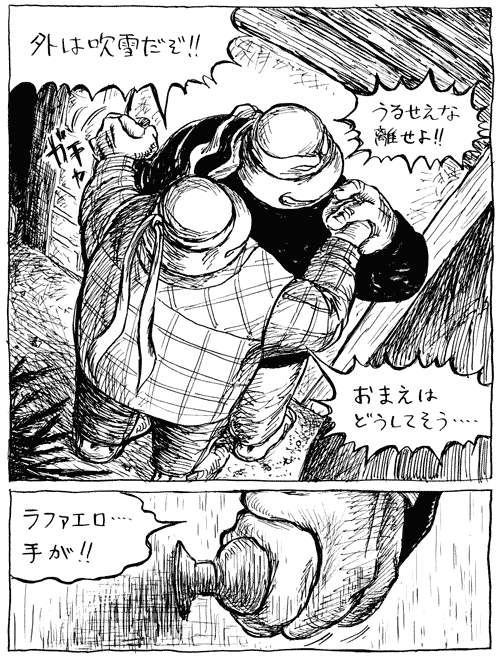
触れたところが水に濡れて湿っていくのがわかった。俺の吐く息は白く立ち上るのに、わめきちらす彼の温度は低く、歯の根が震える音がした。がちゃと僅かに開いた木戸から雪の風が殴り込んできて、扉を押し開け、小屋を揺らす。ラファエロはどこからそんな力が出るのか、俺ごと引きずってでも外へ出ようとする。外は一面の灰と白。風が逆向きになって雪を巻き上げ、木々は槍のように突き立って、空と地面の境目もわからない。氷の風が幼木の黄緑色の葉を容赦なくちぎりとる。
俺は入り口に立ちふさがった。どん、と押されて山積する雪に足がつっこんだ。ごうごうとふぶく風が毛布をはためかせ、折れたマッチを吹き飛ばし、息もできないくらいの地吹雪に俺の体は一瞬宙に浮く。開いていた木戸が風にばたんと跳ねる音。彼の手が伸びて、強い力でもって小屋の中へ引きもどされる。ばんっと背後で扉が閉まる音。
風が止み、俺たちは狭い小屋で抱き合って、互いの呼吸を聞いている。
ラファエロの心臓が、どっど、と激しく脈打つのを感じた。俺は他の星からワープしてきたような浮遊感に足をふらふらと彷徨わせながら「頼むから」と、冷たいシャツの肩口に囁くと、いかっていた肩がすとんと落ちる。そして、ぐるると唸る声が、
「……分かったから、離れろ」
俺は彼の顔色をうかがいながら、まわしていた腕をゆっくりと解いた。触れる腕や肩からすっかり力が抜けているのを確かめ、眉間に寄った皺が怒りではなくて、たんなる居心地の悪さから寄せられているのだとわかるまで、手を離さなかった。
「天気予報では、」
俺は俯いて、彼の胸のあたりにささやきかける。
「夕方には止むといってた」
「そうか」
小さく言って、彼は木造の椅子にどかと座り腕を組んで押し黙る。俺は彼から少し離れたところに座って、落ちた毛布を拾い、ぱたぱたと雪を払った。濡れたモミの木を脇におしやり、毛布を広げて彼と、俺の膝にかけようとするが長さが足りず、俺はちらとラファエロを見て、あけていた間隔を詰めた。彼は何も言わなかった。俺は彼の組んだ腕の間に毛布の端をはさんで足元までくるまるようにしてかぶった。裸足の足を引き寄せて、毛布の中でごしごし擦りながらごうごう鳴る風の音に耳を澄ませた。しばらくそうしていると、とろんと頭の中がしびれてきて、重しをのせたように全身が沈み意識が遠のいて、突然しゃぼんみたいにぱちんと割れる。俺は慌てて鼻先を毛布にこすりつけて寒さに唸りながら、薄暗い小屋の中に目を走らせた。角に小さな棚があって、そこに麻でできた布袋が口を開いた状態で置いてあった。慌てて中を開けたようなあとがあって、土の床に割れたカンテラと、着火剤の包装紙とマッチの箱が塊になって落ちていた。毛布を肩までかぶっても吹き込んでくる風を遮ることはできなかった。割れた窓には板が打ち付けてあったが、吹雪はその隙間から小屋の中へ入ってくる。吐き出す息は細く単調になり、頭痛は低いビートのように続いていた。隣に座るラファエロは、じっと動かず、静かに顔を伏せたままだった。不安になって呼ぶと、彼は閉じていた目を開けて、
「……おまえ、どっか行くのか」
「……いくって、どこへ」かちかち歯が鳴った。
「違うならいい」
彼は目を閉じて、長く息を吐いた。俺は冷たい自分の足を握りこんで、
「だったらどうする」
ラファエロの目がひらく。赤茶の瞳がじっと俺をみつめる。俺はがたつく声で、
「俺が、もし、どこかへ行くと言ったら、おまえはどうするんだ」
彼は笑い混じりに、
「そりゃあ、まあ、せいせいするだろうよ」
なぜだか喉が詰まって、俺は握り込んだ足の指を殊更丁寧にもみほぐした。ラファエロは少しだけ間延びした声で続ける。
「じゃあおまえはどうするんだよ。俺がどっかへ行くっつったら」
予期していなかった問いに、俺はぴたと手を止めた。冷たかった足にじんわりと熱が戻ってくる。ラファエロはまっすぐ前を見ていたが、俺が何か言うより先に、ああ、とため息をついて、聞いたことのないような弱々しい声で、
「ほらな。考えもしねえ……おまえ、俺はどこにも行かねえって思ってんだ」
ラファエロはごつと頭を壁に打ち付けて、くそ、とひとりごち、乾いた声で笑いだす。
「そうだな。きっとそうだ。おれはどこにもいかねえよ……」
「俺だってそうだ」
「はっ……どうだか…………」
どこか遠い、夢見るような口調で彼は言った。呼吸が酷くゆっくりになり、深く刻まれていた眉間の皺がやわらいでいく。
「ラフ」
まぶたが落ちて、体がずるずるとかしいでいく。俺は彼の腕を掴んで引き寄せた。体は氷のように冷たく、組んでいた腕がだらんと垂れてぶらさがる。ぞっとして、俺は彼の肩を掴んで揺さぶった。彼はうっすら目を開けて、うむ、と喉の奥で答えるがまたすぐに意識をそちらへやってしまう。俺は彼の体に毛布をまるごとかけると、地面に散らばるマッチをかき集めた。転がっていたモミの木から細い枝をむしりとって曲げて柔らかくし、暖炉にあった生木の先に折れて短くなったマッチを束にして結びつける。それから落ちていた斧をとり、麻袋の置かれた棚めがけて打ち下ろす。がしょん! と棚は真っ二つになって割れる。俺は斧をなげすてて棚木をはぎ取り、内側の乾いているところを暖炉に積んで、散った木くずを両手で集めて山を作ると、その上でマッチをこすった。ぱちっと一瞬小さな火が出たが、マッチの半分はすぐに消えてしまい、残った小指の爪ほどの火を、吹き込む風からかばいながら、なんとか木くずに移した。風よけにした俺の手の中でちいさく燃えていた火は、残っていた着火剤に燃え移ってぼっと大きくなる。手を焦がすほど熱く燃える火にほっとして、俺はばらばらにした棚木を濡らさないように持って、慎重に、一つずつくべていった。ときどき椅子に戻って彼に呼びかけ、叩いてゆすり、うむと答えるのを聞いて、また暖炉にいって木をくべる。そうしてしばらくは火を絶やさないようにしていたが、棚木が燃え尽きてしまうと、小屋はまた元のぞっとするような冷たさに戻ってしまった。燃えて黒くなった木をとり、まだ暖かいそれを毛布の中に入れて、俺はとんとん足踏みしながら、一か八か外へ出て行ってうまくいけば車まで戻れるんじゃないだろうかと考えたが、そばに転がるモミの木を見て、これよりももっと大きな木が倒されそうになっていたのを思い出した。
俺は投げ出されていた彼の足を椅子の上に抱え上げて、自分も一緒に毛布にくるまった。がたがた震えながら彼の大ぶりの甲羅を抱え込んで触れるところすべてをごしごしとこすった。吹雪は益々強くなって壁を叩いていた。みたことのないくらい穏やかなラファエロの顔をべちべちと両手で叩いて、うっすらと開いた口に自分のを押しつけた。彼の喉がごくりと上下する。俺はもう吸い付いているのか、呼びかけているのかよく分からない状態で、残った熱をなんとか与えようとした。濡れたシャツを脱がせて、その手の片方ずつにぬるい息をふきかけた。甲羅を拳で叩いて、中に響かせ、口づけ、呼び、冷たい唇を噛んだ。
そうしていると、彼はやや億劫そうに答えはじめ、吐く息に色が混ざる。下を脱がせようとすると、ぶるりと体を痙攣させて目を開く。俺は濡れたスウェットをまくり上げて、彼の冷たい足を掴んだ。うっ、と苦しげな声があがった。俺は彼の足の片方をあぐらをかいた腹のところに抱え、もう片方を両手で持って、足の指の間に手の指をつっこんで、ぐいぐい曲げて動かした。ラファエロはこんどこそ跳ね起きて、どっと冷や汗をかきながら俺の手を振りほどこうとした。すかさず俺は指の付け根をぐりと揉む。
「ぃってえだろてめえぶっとばすぞ!」
「おまえが悪いんだ、我慢しろ」
「ういっつ……くっそ……死ね」
「いつかは死ぬさ」
「じゃ消えろ」
「どこへ」
「見えないところに決まってんだろ、うっとおしいんだよ」
俺は俯いて彼の分厚い足の爪を撫でた。白っぽくなっていた肌が濃い緑色に戻って、皮膚の下を走る細い管が血を巡らす音を聞いた。俺達の皮膚は人よりも厚くて堅い。冷たいコンクリートの上を走ってもすりきず一つできず、爪も短くて層になっている。ひとつひとつの骨は太く、さわると出っ張った関節から小気味良い音がする。甲羅なんかはもっと堅い。触ろうが叩こうがそこはただの空洞だ。たとえ割れて砕けても、治ればもっと堅く、厚みを増して鈍くなり、そのうちにどんな痛みも受け流すようになる。
彼は気絶した俺を背負って長いこと歩き回ったんだろうか。足裏に水疱ができていて、丈夫な皮は剥け、爪は紫色になって死んでいた。頭を締め付けるような鈍痛とともに、鼻がつんと痛くなって奥から暖かいものが、ぽたんと落ちる。それはつま先の上で黒い染みになる。拭うと袖口に赤いものが伸びた。顔をあげるとラファエロが青白い明かりの中で、俺をみつめている。俺はぼそ、と
「鼻血だ」
と言って鼻をすすり、揉む足を変える。
俯いていた顔をべし、と冷たいものが張った。みるとラファエロが濡れた自分のシャツを持って、俺の鼻先を拭っていた。黙ってされるがままになっていると、彼はとつぜん俺の顔を両手でわしづかみ「だめだ」と吐き捨てた。がちがち言う歯がかすって、ぬるい息がかかる。彼の足が腹をどんと蹴る。一瞬息がつまってあえぐのをわって入ってくる。俺は咳き込みながら、彼の首を掴んで「ちょっとまて」と言うが、声は空気になるだけだ。木造りの椅子がみしいと音を立てる。
肉厚の舌が這い回っていまにもつりそうなおれのを噛んだ。鼻血のせいで口の中は鉄の味がしていて、溢れる唾液に血が混じった。息ができなくて力任せに彼の胸を押しのけようとした。彼はさらに強い力でどんっと俺を蹴りたおし、ごろんと仰向けになった俺のジーンズに手を掛けてずり降ろそうとする。彼のスウェットの前にわずかな染みがあるのがみえて、俺が目を背けると彼はまた、は、と鼻で笑って、
「その気になってんだから手伝えよ」
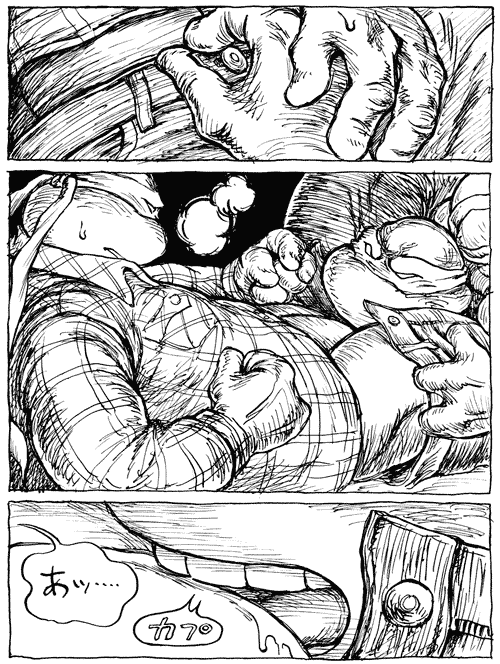

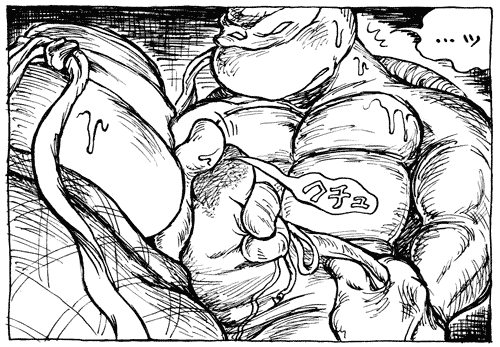
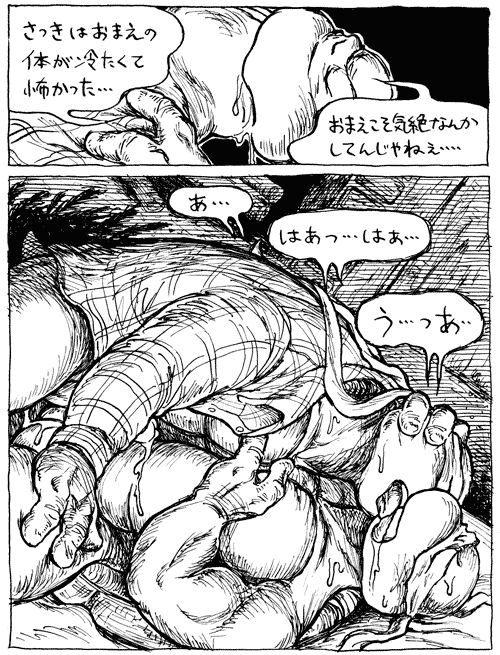

ぬるぬるいう腰を互いにこすりあわせ、息も荒く彼の膝が椅子につくんじゃないかというくらい乱暴に押さえつけた。椅子がきしんで、籠もった息を漏らしながら彼もぐいぐいとおしつけてくる。根本から先まで、堅い皮膚と熱い彼のとをいっしょくたにこねると、つま先まで貫かれたような快感に満ちて、彼の腹めがけ、ぶるりと震えて吐き出した。
ぶつかった胸が同じ早さで上下した。しらむ景色に赤くもつれるマスクの端と、ぐうんとのどを鳴らして達するラファエロの顔がある。その目にはだらしなく口を開いた俺がいて、いつも鏡で見るような装った自分とはまるで違った姿をしている。彼はそれを知っているのか、息を荒げながら意地の悪い笑みを浮かべている。俺があからさまに後ろに手を回しても、目を細めるだけでその視線は動かない。椅子をいっそうきしませて、彼のはちきれそうなももをめいっぱいにもちあげる。つかまえた彼の尾はふっくらとして全体を前と同じくらい濡らして光り、つまむ指を押し返す。そのまま奥まったところへ指を伸ばし、ぎゅうとしぼんで濃い色のところを弄ってしめらせていると、彼がべとつく腹から下へと、自分の手を差し入れてくる。
収縮を繰り返す瞳が、歯をむきだしにする俺とそこから垂れる唾液や汗を追って、べろりと舌を這わせてなめとった。彼は体をひねらせ、なぶる俺の手に手を重ねると、自分のと一緒にそこへ押し込んだ。彼の足が俺の甲羅のうえで踏ん張る。内側のうすい壁を破ってしまいそうな強さで奥へ奥へとわり進んでいく。合わさった口の中で呼びかけると、彼の目はまっすぐ俺を捕らえて、俺の頭を強く抱く。なかは生き物みたいに波打っている。脈打つ鼓動を感じ、彼の指と、俺のとが中でからまって、ちゃくんちゃくんと響く音が、次第に大きくなっていく。
今にも消えそうな理性の灯火を手に、俺はまとわりついていたジーンズの両足をすりあわせてばたばたと慌ただしく脱ぎすてる。吐く息が真っ白になって立ち上る。何度目かもわからない口づけ。歯と歯が擦れ合うわずかな振動も、溢れる唾液を飲み込む音も驚くほどよく聞こえる。「れ、おっ」声。彼がしめつけ、全身からむっとするようなにおいを立ち上らせる。ぶるんと震える前は太いところが深い緑で先は濃い赤。彼の手がそわそわとマスクの結び目や、シャツの襟を弄る。足首を掴んで肩までひっぱりあげ、ごろごろ転げる甲羅の下に膝をわりこませると彼の頭が椅子にぶつかって「いっ」。彼はうめいて両手をきしむ椅子につき、膝で俺の頭をがつんと一発。鼻からまた血がつたって落ちてくる。
どこもかしこも熱かった。頭の中まで燃えるようで口は血の味がしていたし、外は吹雪で、俺たちは二人きりだった。俺は伝う血を舐め、躍動するももと紅色になったひだに鼻先をうずめて、舌をねじ込んだ。先をとがらせ、ざらついたところをつつくと隣り合わせた肌からじわっと汗が滲みでる。熱い息をおもいきり風船みたいに吹き込んだ。彼がびんっと緊張し、感極まった声と共に目の前で腹が大きくそげたかと思うと、再びどたんと後ろに倒されて俺は粗末な小屋の壊れそうな天井を見上げるようになる。顔にぽたぽたと熱いものが垂れてきて、みると馬乗りになった彼が大きな体を曲げて、俺を見下ろしているところだった。その目はいつにも増してきつくつり上がり、瞳は赤混じりの茶色で息も絶え絶えにかぶさってきてめちゃくちゃにかみ合う。合間から、くそ、だの、ちくしょう、だの悪態が混じり、もうどちらのものかわからないくらいもつれあい「レオ」また声。こわばった俺は熱く蠢くところへ包まれてもう頭の中は一面の、白。
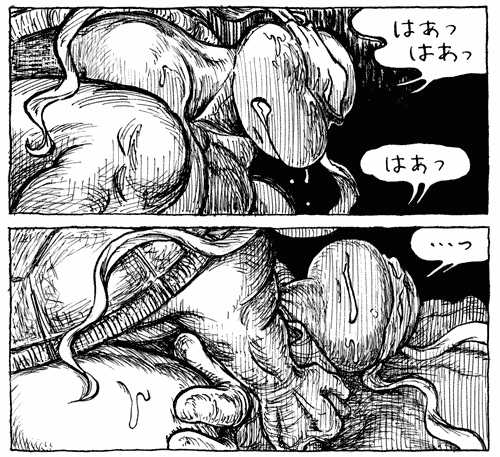
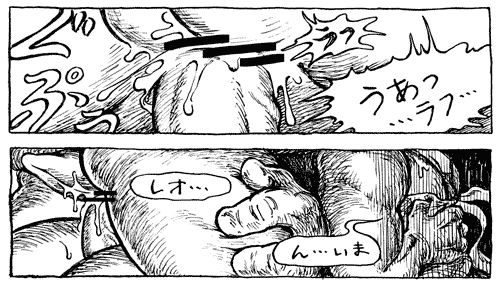
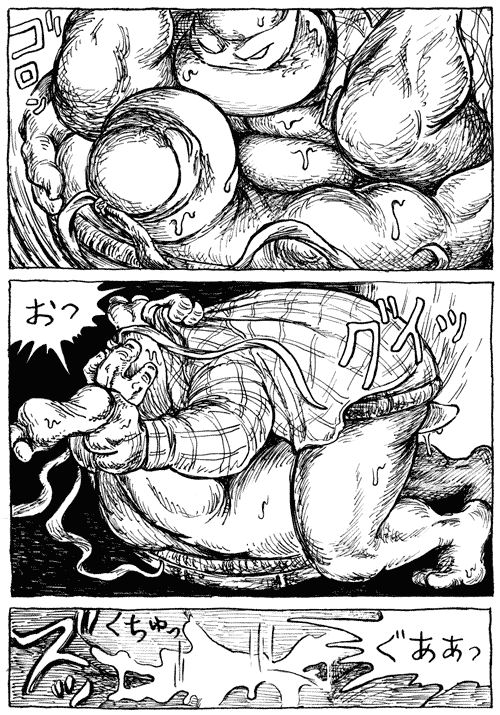
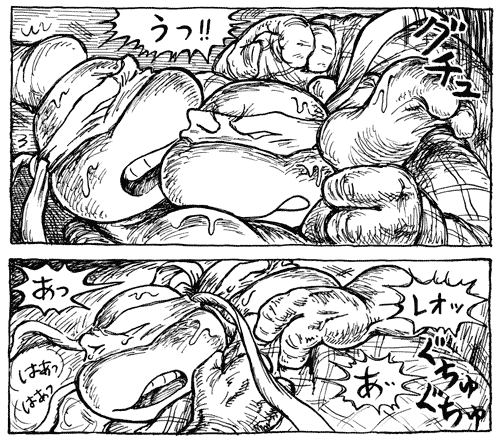
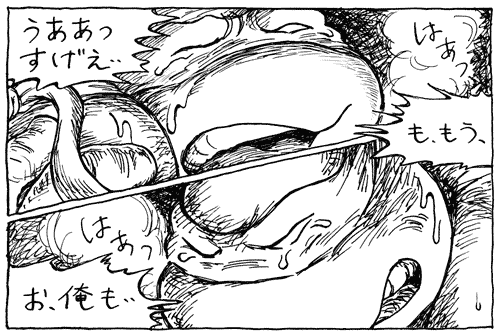
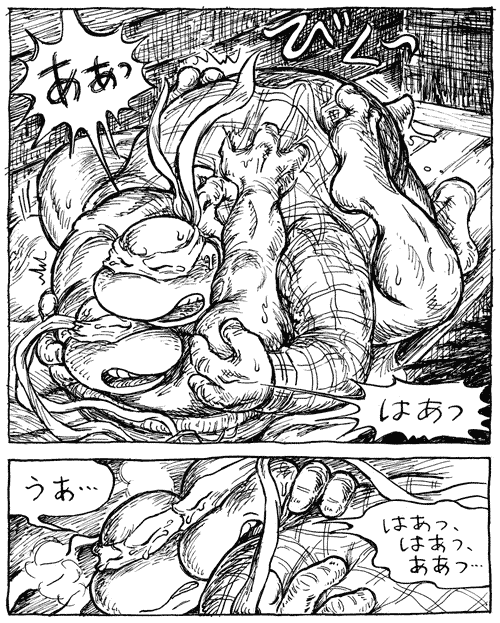
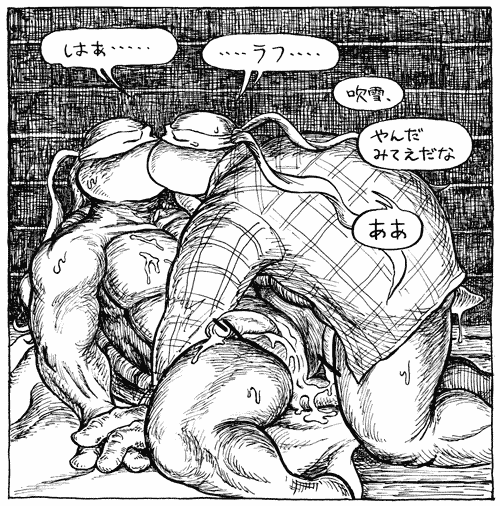
ほこりっぽい光が差しこんで、上下する彼の肩と首と胸を伝う汗を追った。
風はいつのまにか止んでおり、空気は鋭くとがって肌を突き刺した。しんとした小さな小屋にあるのはきしきしいう椅子と、しわの寄った毛布と、俺の靴。
風はいつのまにか止んでおり、空気は鋭くとがって肌を突き刺した。しんとした小さな小屋にあるのはきしきしいう椅子と、しわの寄った毛布と、俺の靴。
地面に落ちて裏返っていたのを拾おうすると、彼は「よっ」と威勢の良い声をあげて起き上がって、俺たちはちょっと疲れた顔で向き合い、お互いのでまみれた下腹を毛布でふきながらもごもごと話しをした。
彼は自分のシャツの腕をちぎって足に巻いてインディアンが履くような靴をつくった。俺はうまく動かない指でシャツのボタンを留めようとしたが、何個かなくなっていたので諦めてそのままにした。散らばったマッチを集めて麻袋に放りこみ、立てかけてあったのこぎりをとってその歯のかけたところに指を滑らせている間、彼は汚れたスウェットをはきなおして渋い顔をしていた。唸って頭をかきながら小屋を見回し、椅子にある毛布を手にすると、ばっばっと二度三度叩いて汚れた方を裏側にして上から羽織って端を結んだ。毛布は丁度膝まで隠れるくらいの長さになって、メキシコのインディアンみたいになった。苦い顔をして見ていると、彼は麻袋をもぎとって、
「はやくしろよ」
「わかってる」
彼は木戸に手をかけた。振り返り、ジーンズに足を通そうと飛び跳ねる俺の汚れた腹や濡れて光る内股を余さず眺めていた。俺が身支度を終えて木戸の前に立っても彼はドアノブに手をかけたまま、俺をじっと見ていた。視線は俺より少し高めで、それが即席のインディアンブーツのせいなのか、たんなる身長差なのかわからなかったが、あまりいい気はしなかった。彼が低い声で、
「おれがほんとうにどっかに行くっつったら、どうする。」
俺は答えられなかった。想像することもできなかった。あとに続く沈黙が恐ろしくて「先生がお許しにならないだろ」と思ってもいないことを言った。彼は痛いところをつかれたという顔をしたが、それももしかしたら俺と同じ理由からしてみせた、ふり、なのかもしれなかった。
「結局真面目か。……ったく」
「今日のことだって、どう報告する。しばらくは外出禁止に決まってるだろ」
「うるせえなわかってるよ」
わかってんだよ、と彼はもう一度だけ念を押すように言って、木戸を開いた。戸は積もった雪に阻まれて、ずずずと重たい音をたてた。水色の空に黄色い太陽があった。地面は一面の雪に覆われて、足を踏み出すと溶けかけた表面がぎゅっと堅い音をたてた。吹き抜ける風は叩きつけるような冷たい風ではなくて、湿っぽさをぬぐい去るような新しい風だった。ばたんと後ろで戸を閉める音がして、彼が寒さに呻りながら俺のすぐ横に立つ。疲れた横顔が午後の太陽に照らされてほんのり赤くなる。白い息を吐きながらあたりをぐるりと見回した彼は、広がる雪原をその目に映して満足げに微笑み、ざくざくと歩き出した。赤色のマスクをたなびかせ、背中に荷物を背負ってどんどん歩いていく。突き立ったモミの木は積もった雪をふるい落として枝を伸ばし、黄緑色の葉を太陽にさらしている。薄色の長い影が伸びてきてその手に彼を捉えて連れていく。
いま動かなければ、このまま留まっていれば、全てのしがらみから解放されるような気がした。背後にはうっそうとした森があって、その腹に計り知れぬ闇を孕んで待っており、俺の知らない奇跡や息づく生命をみせてくれるんじゃないかと思った。風は冷たく、枝は鷹の爪のようにとがっていたが、静まりかえる木々の暗さはどうしてか俺の体の深いところを掴んで揺りうごかした。
顔をあげるともう、ラファエロはぽつんと小さな影になっていた。彼は一度だって振り返らなかった。その隣りにもうふたつ、背丈の違う影があって、一人が飛び上がりながら大きく手を振っていた。おおーい! と呼ぶ声があたりに響き渡った。
「レオ!」
声はこだまになって木から木へ飛び移り、俺のところへやってくる。立ち尽くす俺のもとへ向こうからやってくる。大地に根をはる足を必死で動かした。間違って生えた枝のように手を振った。先頭をきってきたのはミケランジェロで、降り返した手に刀を一本持っており、連なるモミの木のひとつをそれで指し示す。それは中でも背の高い、青年期に差し掛かったモミだった。横一列に肩を並べる幼木たちの中でそいつはただ一人、そしらぬ顔して立っていた。ぐんと伸ばした幹は太く、枝はすき間なく均等に生えそろい、先はまっすぐに天に向かっていた。
ミケランジェロがちょっとつんのめりながら走ってきて、持っていた刀をぶうんと放り投げる。刀はたよりなく掲げた俺の手めがけ綺麗な放物線を描いて、

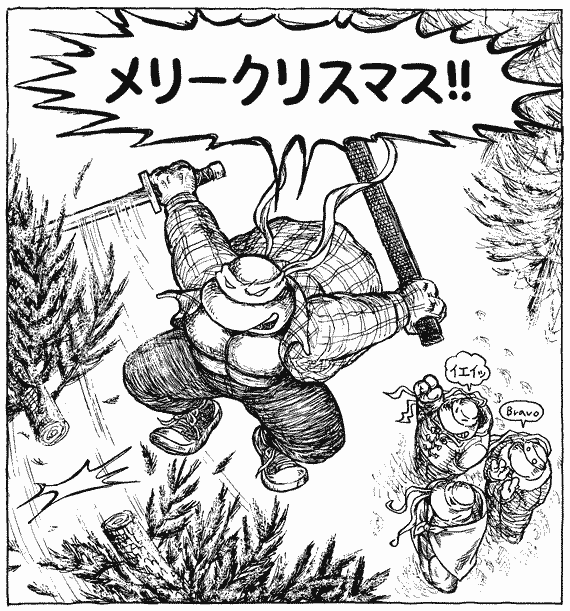
おしまい。